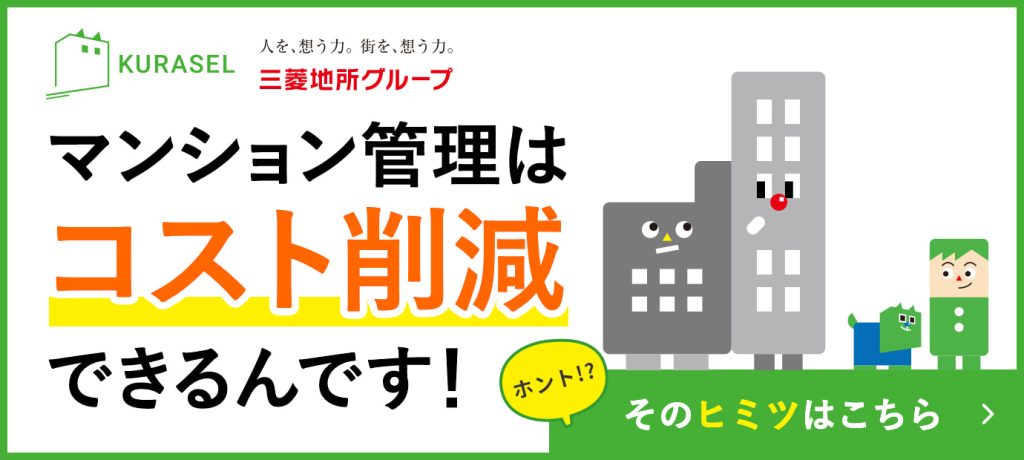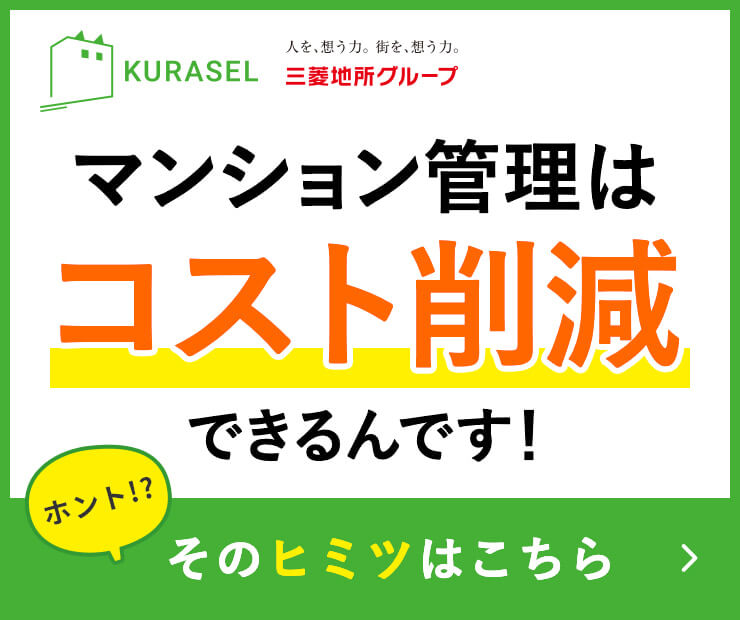マンション大規模修繕の工事内容について。トラブル対策なども解説

12年~15年ごとに実施されるマンションの大規模修繕工事。
管理組合の方々は修繕工事に関する知識や経験がない方がほとんどでしょう。
とはいえ、大規模修繕工事は大きな費用がかかります。
その原資は各区分所有者が毎月コツコツと積み立ててきた修繕積立金です。
大切な資金を有効活用するためには、管理組合の方々が知識を身に付けていく必要があります。
今回のコラムでは大規模修繕工事の内容や、トラブル対策などについて解説していきます。
関連記事:大規模修繕を検討する段階から工事終わりまでの進め方を解説!
関連記事:マンションの大規模修繕で注意すべきことは?費用・周期・時期について
INDEX
大規模修繕工事とは?なぜ工事の必要があるの?

まず大規模修繕工事の目的について再確認しましょう。
大規模修繕の目的は、経年劣化によって傷んだ箇所を補修し、マンションの性能や快適性を新築に近い状態に回復させることです。
これにより、マンションにお住まいの方たちの快適さを維持し、外壁タイルの剥落などから居住者や地域住民を守り、安全性を確保します。
そして、マンションの資産価値を維持することにもつながります。
劣化が進み、居住快適性を失ったマンションは、資産価値が下がってしまいます。
資産価値が下がると、売却が難しくなり、結果としてマンションの高齢化や空室化が進み、管理や運営に支障が出る恐れがあります。
これが負の連鎖となり、ますます売れにくい状況に陥ってしまうこともあります。
一見すると劣化しているように見えなくても、コンクリートの内部の劣化が進んでいるケースも決して珍しくありません。
雨水や空気が内部の鉄筋まで浸入すると、錆びが生じ、耐久性が低下します。
また、外壁タイルが剥落すれば、地域住民にも被害が及ぶ可能性があり、管理組合が賠償責任を問われることになります。
大事に至る前に、適切な大規模修繕を実施することで、経年により劣化したマンションの性能や機能を回復させ、快適で安全な状態を維持できるのです。
関連記事:マンションの修繕積立金、相場はいくら?そもそも必要なの?あらゆる疑問を解消!
大規模修繕工事の内容

大規模修繕工事と密接に関係しているのが長期修繕計画です。
長期修繕計画は、将来の大規模修繕工事をいつ、どの程度の費用で実施するかを計画するものです。
月々の修繕積立金の額についても長期修繕計画に基づいて設定されるのが一般的です。
長期修繕計画に盛り込む工事内容と周期は以下の通りです。
| 工事項目 | 内容 | 周期 |
|---|---|---|
| 屋上防水 | 補修・修繕 | 12年〜15年 |
| 撤去・新設 | 24年〜30年 | |
| 床防水 | 修繕 | 12年〜15年 |
| 外壁塗装 | 塗装 | 12年〜15年 |
| 除去・塗装 | 24年〜30年 | |
| 躯体コンクリート補修 | 補修 | 12年〜15年 |
| タイル張補修 | 補修 | 12年〜15年 |
| シーリング | 打替 | 12年〜15年 |
| 鉄部塗装 | 塗装 | 5年〜7年 |
| 建具 | 点検・調整 | 12年〜15年 |
| 取替 | 34年〜38年 | |
| 屋外鉄骨階段 | 補修 | 12年〜15年 |
| 取替 | 34年〜38年 | |
| メーターボックス扉 | 取替 | 34年〜38年 |
| メールボックス | 取替 | 24年〜28年 |
| 給水管 | 更生 | 19年〜23年 |
| 取替 | 30年〜40年 | |
| 貯水槽 | 補修 | 12年〜16年 |
| 取替 | 26年〜30年 | |
| 給水ポンプ | 補修 | 5年〜8年 |
| 取替 | 14年〜18年 | |
| ガス管 | 取替 | 28年〜32年 |
| 空調・換気設備 | 取替 | 13年〜17年 |
| 電灯設備 | 取替 | 18年〜22年 |
| インターネット設備 | 取替 | 28年〜32年 |
| インターホン設備 | 取替 | 15年〜20年 |
| 屋内消火栓設備 | 取替 | 23年〜27年 |
| 自動火災報知設備 | 取替 | 18年〜22年 |
| 連結送水管設備 | 取替 | 23年〜27年 |
| エレベーター | 補修 | 12年〜15年 |
| 取替 | 26年〜30年 | |
| 機械式駐車場 | 補修 | 5年 |
| 取替 | 18年〜22年 | |
| 外構 | 補修・取替 | 24年〜28年 |
長期修繕計画に盛り込む工事内容=大規模修繕工事で行う工事内容と考えて良いでしょう。
マンションによって状況は異なりますが、通常、12年前後の周期で設定されているものを1回目の大規模修繕工事で実施します。
その際、劣化状況などに応じて、近い周期の修繕工事も同時に実施することが一般的です。
これは、工事に必要な経費や人件費をまとめてしまうことで、コストを削減できるからです。
関連記事:長期修繕計画の作成にかかる費用を紹介!エクセルでの管理方法も解説
大規模修繕の費用について

大規模修繕には、一戸あたり75~125万円の費用がかかります。
令和3年に国土交通省が実施した「マンション大規模修繕工事に関する実態調査」によると、半数以上が一戸あたり75万円以上の費用を負担していることが分かります。
マンション全体の修繕費用だと中央値で7,600万円~8,700万円程度。
平均値で1億1,000万円~1億5,000万円になる計算です。
ただし、これらの金額には共通仮設費は含まれていません。
また、一般的に2回目の大規模修繕工事の方が1回目よりも費用が高額になる傾向があります。
これは2回目では、修繕すべき箇所が増えたり、同じ箇所であっても補修ではなく交換対応となったりするためです。
同様に、3回目の大規模修繕工事も2回目よりも工事金額が高額になるケースが多いようです。
大規模修繕でよくあるトラブルとその対策

大規模修繕工事中にトラブルが発生することは決して珍しくありません。
トラブルが起きたときに慌てるよりも、事前にどんなトラブルが起きやすいのか、また、トラブルが発生した際にはどのように対処すべきなのかをあらかじめ管理組合内で確認しておくと良いでしょう。
大規模修繕工事中に発生しやすいトラブルは以下の6つです。
①マンション居住者とのトラブル
②近隣住民とのトラブル
③修繕費用に関するトラブル
④各業者とのトラブル
⑤修繕委員会内でのトラブル
⑥空き巣被害
それぞれの項目について順番に見ていきましょう。
①マンション居住者とのトラブル
居住者が生活したまま実施する大規模修繕工事では、居住者とのトラブルが起きやすくなります。
マンション居住者との代表的なトラブルは次の3つです。
- 工事に協力的でない
- 部屋の中を見られてしまうのが嫌
- 入室が必要な作業でのトラブル
・工事に協力的でない
大規模修繕工事をスムーズに行うためには、居住者の協力が不可欠です。
工事中はバルコニーやエレベーターが使用できない、騒音が発生するなど、通常の生活を送れないストレスから、非協力的な発言や態度を取る居住者が現れるかもしれません。
居住者とのトラブルの主な原因は、コミュニケーション不足です。
工事の重要性が居住者に伝わっていなかったり、居住者の声に耳を傾けられていなかったりと、工事前から良好な関係が築けていないケースも。
・部屋の中を見られてしまうのが嫌
足場を組んで窓のすぐ近くで作業をする場合、カーテンが開いていると部屋の内部が容易に見えてしまうことがあります。
実際は見ていなくても、作業員の立ち振る舞いや視線によっては、部屋の中を覗かれたと感じられてしまうこともあるようです。
これは、足場での作業日時や、カーテンを閉める必要性などが十分に周知できていないことが主な原因です。
作業員においても、誤解を招く行動をしないよう徹底してもらう必要があります。
・入室が必要な作業でのトラブル
大規模修繕工事中には、各部屋のドアやサッシの交換、給排水管の補修など、工事業者が専有部内に立ち入ることがあります。
もちろん事前に通知し許可を得た上での入室となりますが、中には入室を望まない居住者とのトラブルも生じることがあります。
工事業者が一方的に入室日時を決めるのではなく、居住者の希望時間に合わせたり、最低限の入室で作業ができないか検討したりと、可能な限り居住者に配慮してもらうようにしましょう。
他にも「作業員の服が汚れていて部屋が汚れてしまった」「作業員がとてもタバコ臭くて気分が悪くなった」といった苦情もよく聞かれます。
マナーの問題でもありますが、あらかじめ工事業者に注意を促しておくと良いでしょう。
②近隣住民とのトラブル
大規模修繕工事はマンション内の居住者だけでなく、近隣住民とのトラブルに発展することもあります。
特に多いのが、騒音や臭気、ホコリなどによる苦情です。
大規模修繕工事を行う以上、ある程度の騒音やホコリの発生は避けられませんが、近隣住民の健康にも影響することがあるため、慎重に対応しなければなりません。
工事前に近隣住民に対して、工事期間や内容について説明会を実施したり、個別に自宅を訪問して説明したりすることで、トラブルを最小限に抑えることができます。
また、住民が在宅していることが多い土日祝日は、音を立てる工事を控えるなどの配慮も欠かせません。
当然ながら大規模修繕工事が終わった後も近隣住民とのお付き合いは続きます。
良好な関係を築いていくために無用なトラブルは極力回避しておきたいですね。
③修繕費用に関するトラブル
大規模修繕工事の費用を見積もる際、外壁タイルの補修など、足場をかけないと正確な見積もりができない箇所については、仮の金額で見積もっておき、着工後、実際に工事した数量と単価に基づいて、費用を清算するのが一般的です。
この仮の金額は通常、少し余裕を持って見積もられます。
しかし、着工後に予期せぬ不具合が見つかり、工事個所が増えた場合、修繕費用も高くなり、トラブルになるケースがあります。
修繕費用が高くなってしまい、修繕積立金が不足した場合、考えられる対策は以下の3つです。
- 修繕積立金の追加徴収
- 修繕積立金の値上げ
- 住宅金融支援機構や金融機関からの借り入れ
修繕積立金の追加徴収は、費用不足を補う効果的な手段ですが、総会での承認が必要なため、緊急時には時間的な余裕がありません。
また、総会で反対多数により否決されてしまうと徴収はできません。
修繕積立金の値上げ自体は決して珍しい話ではありませんが、現在進行中の大規模修繕工事の不足費用を補うためだけに値上げを行うと、かなり高額な値上げとなる可能性があり、あまり現実的ではないかもしれません。
住宅金融支援機構などからの借り入れ自体は決してNGというわけではありませんが、こちらも総会での承認が必要であり、手続きに時間がかかる場合もあります。
そのため、進行中の工事の不足費用を補う手段としては現実的ではありません。
つまり、工事が始まった後に修繕積立金が不足する状況は回避すべきです。
そのためには、修繕積立金をしっかり貯めていく取り組みが必要です。
また、既存の修繕積立金内で必ず収まるように、工事項目の精査や発注業者の選定を慎重に行う必要があります。
④各業者とのトラブル
工事業者やコンサルタントとのトラブルが生じることも想定しておきましょう。
主なトラブルの内容は以下の通りです。
・工期の大幅な遅延
工期が大幅に遅延する理由の一つとして、まず挙げられるのが天候です。
雨天時は工事を中断する場合があるため、雨の日が続くと工期が延びてしまいます。
また、工事が始まってから設備の仕様や建材のグレードを変更することによっても、工期が遅れるケースもあります。
もちろん、工事業者側の事情や都合で遅延することもありますが、遅延が生じた際は、その原因を管理組合側も理解するようにしましょう。
その上で、工事業者に改善を申し入れたり、ペナルティを課したりするなどの対策を検討しましょう。
遅れが生じているからといって何でも工事業者にクレームをつける姿勢だとトラブルに発展してしまうことがあります。
・施工不良があった
大規模修繕工事が完了した後には、施工後2~3年程で雨漏りやタイルの剥がれなどの施工不良が発生するケースがあります。
もし施工不良が見られる場合は、すぐに施工会社に連絡をしましょう。
保証内容や保証期間によっては、無償で対応してくれることもあります。
施工不良に関しては施工後に発覚するケースが多いので、事前の対策は難しいところですが、どんな会社でも施工不良は起きる可能性があると考えておくのが良いでしょう。
施工会社の選定段階からアフターサービス対応をどこまで行ってくれるかを採用基準の一つにする必要があります。
・施工後に費用の追加請求をされた
大規模修工事が始まった後、事前調査では特定できなかった躯体の劣化や配管の不具合などが判明する場合もあります。
そのような場合、追加工事が必要となり、それに伴う費用も追加で請求されます。
もし追加工事や費用が発生する場合は、工事を進める前に必ず施工会社からの説明があります。
その際、施工会社の説明をしっかりと聞き、なぜその工事が必要なのかを理解しておくことが重要です。
・悪質なコンサルタント会社の談合が判明した
大規模修繕では、悪質なコンサルタント会社との談合によるトラブルが以前から多発していた時期がありましたので注意が必要です。
悪質なコンサルタントとは、工事業者と結託して不当に工事費用を吊り上げるという手法で不当な利益を得ているコンサルタントを指します。
2016年頃に問題視され、数々のメディアがこの問題を取り上げ、2017年には国土交通省が注意喚起文書を公開する事態に至りました。
あれから数年が経過しましたが、悪質なコンサルタントがまだ存在している可能性もゼロではないため注意が必要です。
⑤修繕委員会内でのトラブル
大規模修繕工事を進める上で中心的な存在となるのが、管理組合員で構成される修繕委員会です。
工事業者やコンサルタントの選定も修繕委員会が行うのが一般的です。
修繕委員会内でよく見られるトラブルは「全員が集まれる時間が確保できない」「意見がまとまらない」というものです。
そのため、修繕委員会の理想の人数は、全員が集まりやすい5人程度とされています。
少なすぎても多すぎてもうまく機能しません。
意見がまとまらない原因の1つは、大規模修繕工事に関する専門知識がある方が少ないことも考えられます。
このような場合は、専門知識のある第三者機関の協力も検討すると良いでしょう。
⑥空き巣被害
大規模修繕工事中は足場が組まれることで窓から簡単に侵入される可能性が高まります。
また、オートロックが開いたままになったり、人の出入りが増えたりすることもあり、空き巣にとっては好都合な状況かもしれません。
空き巣被害の原因は、防犯意識の低さにもあります。
工事業者と協力して、以下の4つの対策を検討しましょう。
- 防犯カメラ設置
- サーチライト設置
- 窓サッシ用補助鍵の設置
- 作業員共通の服や目印
マンションにおいては、工事業者の選定基準として、防犯対策の実施方法も考慮することが重要です。
工事業者を選定する際には、価格だけでなく、工事期間中の防犯対策の実施計画も含めて慎重に検討しましょう。
関連記事:必要?大規模修繕工事コンサルタントの役割と選び方とは
大規模修繕における業者選びのポイント

大規模修繕工事業者を選ぶ際、どのようなことに注意して選定すれば良いのでしょうか。
一般的には以下のような項目を選定基準にしているマンションが多いようです。
- 会社規模
- 経営状況
- 実績(マンションの改修工事の売上高、元請の割合など)
- 会社立地(近くに支店があるか)
- 大規模修繕工事瑕疵保険の対応可否
また、それ以外には以下のような切り口で考えてみると良いでしょう。
①マンションを建築した業者にこだわらない
②区分所有者、理事と密接な関係にある業者は避ける
③プレゼンテーションで社風を見極める
④現場監督予定者の人柄・能力を知る
⑤工事保証・アフターサービスの内容を知る
①マンションを建築した業者にこだわらない
大規模修繕工事の場合、マンションを建築した会社でないとできない工事はほぼありません。
建築した会社だから安心感があると感じるかもしれませんが、管理組合としてはマンションの建築業者にこだわらず、複数の選択肢をフラットな目で検討することが重要です。
その方が工事内容や工事金額も適正となる可能性が一層高まります。
②区分所有者、理事と密接な関係にある業者は避ける
大規模修繕工事の工事業者は管理会社から提案されることも多いと思いますが、まれに、管理組合内から知り合いの業者を推薦されるケースもあります。
推薦される業者が信頼できると思われる場合もありますが、組合員の親族が経営している会社など、過度に密接な関係にある業者の採用は避けた方が良いでしょう。
万が一トラブルが生じた際に、管理組合として主張すべきことを言えなくなる可能性があるからです。
③プレゼンテーションで社風を見極める
複数の工事業者候補を選んだら、最も安価な見積もりを選ぶだけ、単純にそうとも言えないのが大規模修繕工事の難しいところです。
工事期間が長く、居住者にとってストレスの大きな工事となるため、業者選定を誤ると、居住者から批難される可能性があります。
複数の工事業者候補を選んだら、各業者に理事会や修繕委員会に出席してもらい、プレゼンテーションしてもらいましょう。
プレゼンテーションの資料には、会社案内だけでなく、工事中の安全対策やその他会社の重視している点が記載されているはずです。
各業者が重視しているポイントが、管理組合が重視する項目と一致しているかどうかを確認することも重要です。
例えば、合理化やコスト削減、安全管理に関する社員教育の取り組みなど、工事業者がアピールしているポイントが、管理組合の要求と一致しているかなども選定基準の一つにしても良いでしょう。
④現場監督予定者の人柄・能力を知る
施工会社のプレゼンテーションの際には、営業担当者だけでなく、実際にマンションの現場責任者になる予定の方にも出席してもらうようにしましょう。
現場責任者の人柄や能力は、大規模修繕が無事に完了するための重要なポイントになります。
大規模修繕工事には、騒音や振動、臭気などの問題がつきものです。
これらの問題を大きなトラブルに発展させないためには、現場責任者のコミュニケーション能力が不可欠です。
プレゼンテーションの際には、現場責任者に直接さまざまな質問をして、そのようなスキルを持っているかどうかを判断すると良いでしょう。
⑤工事保証・アフターサービスの内容を知る
大規模修繕工事後の保証をしない業者はほぼ存在しないと思いますが、保証内容は各社同一というわけではありません。
業者のプレゼンテーションの際には、工事後の保証やアフターサービスの内容・期間について、どのような契約を予定しているのかを十分に確認する必要があります。
例えば、防水工事では「○年毎にトップコートを再施工することを条件に○年保証」といった条件付きの場合もあります。
保証やアフターサービスの内容は、工事後の維持管理コストを考える上でも、重要ポイントになります。
まとめ

今回は、大規模修繕工事の際に発生する可能性のあるトラブルの内容や、業者選定のポイントについて触れましたが、実はこの2つは非常に密接に関係しています。
良い業者を選定できれば、トラブルは発生しない、または発生しても大きなトラブルに発展しないことが期待できます。
大規模修繕はマンションの一大事業です。
施工した会社でないとダメ、管理会社のグループ会社なら安心、などということはありません。
広い目で業者選定をすること、それが大規模修繕を成功させるポイントの1つです。
でも業者はどうやって探せば良いの?
そう思われた方におすすめなのが、DeNAグループの提供している「スマート修繕」です。
スマート修繕は、大規模修繕などの相見積もりやコンサルタント選定を支援してくれるサービスです。
こちらの会社の創業者は、かつて自宅マンションで理事長をされていた経験があるそうです。
その際の大規模修繕工事において、管理会社から提案される内容に多くの疑問を持った経験から「スマート修繕」をDeNAの新規事業として立ち上げるに至ったそうです。
元理事長目線での事業ということもあり、管理組合目線での提案が受けられることが期待できますし、公正取引を宣言していますので安心感があります。
大規模修繕工事の際は、このようなサービスを活用するのも有効な方法でしょう。
スマート修繕のサービス紹介ページはこちら